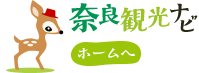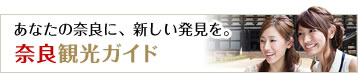興福寺北円堂は、元明太上天皇と元正天皇が藤原不比等の菩提を弔うためのお堂として創建されました。
現在のものは鎌倉時代(1210年)の再建で、国宝に指定されています。
堂内には、仏師・運慶の作である弥勒如来像、無著・世親像などの国宝仏が安置されています。
北円堂は毎年春と秋に特別開扉されますが、今年は夏期も開扉されます。
春秋の特別開扉とは時間が異なりますのでご注意ください。
奈良国立博物館の開館120年記念特別展示
売太神社で毎年8月16日に行われる祭り。昭和5年8月16日当時の童話家 久留島武彦氏らが提唱し、全国童話連盟の人たちによって始められた。全国の童話作家をはじめ多くの人々に「話の神」として信仰される阿礼祭。「稗田舞」をはじめ、子どもたちによる「阿礼さま音頭」や「阿礼さま祭子供の歌」が奉納されます。
立春から数えて二百十日、収穫前の台風の難を避けるために神頼みする風習が山間部の各地区で行われていますが、各地区で様相がずいぶんと異なります。中でも切幡にある神妙神社の風の祈祷は少し変わっています。境内に一対の榊を立て、その周りを氏子たちが「一万度ワーイ」と言いながら、両手で万歳をしてぐるぐる回ります。
西国9番札所、南円堂の内部と本尊不空羂索観音と四天王像(ともに国宝)の拝観ができます。(拝観受付締切16:45)
交通:JR奈良駅から徒歩15分/近鉄奈良駅から徒歩5分
聖徳太子等身と伝えられている秘仏救世観音像の厨子が開扉されます。
一年間仏様につもった埃を払います
薬師坊より鬼が松明を振り回しながら暴れまわる。
帝釈天が鬼を追い払う。
平安絵巻の傑作、国宝信貴山縁起絵巻が期間限定で公開されます
鑑真の再来とも言われ多くの功績を残した覚盛上人
修行中、覚盛上人の肌に止まった蚊を叩こうとする弟子に「自分の血を与えるのも菩薩行である」とおっしゃって戒めた故事があります。
うちわまきは覚盛上人が亡くなった後、弟子が「せめて団扇で蚊を払ってください」と霊前に団扇を供えたことに由来しています。
覚盛上人の命日にあたる5月19日に何千本といううちわが国宝、鼓楼の上からまかれ下で参加者がそれを取ります。